家でどんなフォローをしてあげたらいいのか悩むんだよね…
今回はこんなお悩みを解決する記事を書きました。
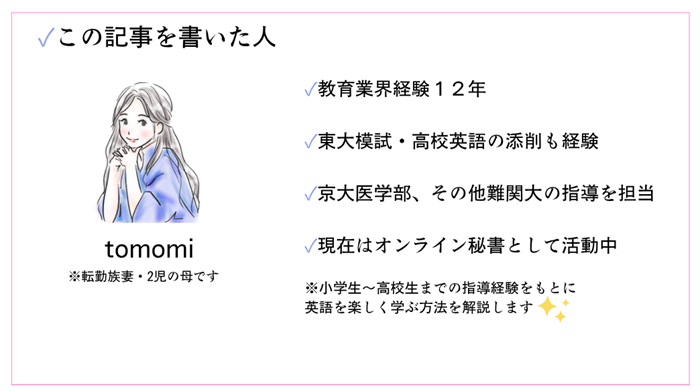
2020年度から、小学3年生で英語活動がスタートし、5・6年生では成績のつく「教科」として英語が本格的に導入されました。
これにより、英語はもはや「中学から始めればいい」教科ではなくなっています。
中学では、小学校で学んだ英語力を前提に授業が進むため、
英語が苦手なまま進学すると、つまずきやすいという声もあるんです…。
この記事では、小学校で学ぶ内容を踏まえて、家庭でできる効果的な学習法を紹介します。
中学入学までに身につけたい基礎力を、家庭学習で楽しくしっかり育てましょう。
この記事でわかること
✔小学校で学ぶ英語学習とは
✔中学校までにどんなことができるようになればいい?
✔家での学習方法
✔苦手になりそうな子にはどうしたらいい?
小学生の英語教育はいつから始まる?

はじめに、小学校の英語学習について解説していきますね。
小学校の授業スタート時期と内容
現在の小学校では、小学3年生から英語活動(外国語活動)がスタート。
5年生からは「教科」としての英語授業が正式に導入されています。
| 学年 | 年間授業数・授業時間(45分) | 内容の特徴 |
| 小3〜4年 | 約35回/年・週1時間程度 | 歌やゲーム中心、聞く・話す主体 |
| 小5〜6年 | 約70回/年・週2時間程度 | 読む・書くを含む教科英語型授業 |
具体的にはこういったカリキュラムです。
小学3〜4年生(外国語活動:約週1回・年間35回)
- 目的:英語に慣れることがメイン
- 学習内容:挨拶・簡単な英語フレーズ(例:"Hello" "My name is...")、歌やゲーム、絵カードなどを使った実体験型学習
- 評価:通信簿には記載なし。発音や理解より「経験」が重視されます
小学校3年生からの授業では英語に「慣れ親しむ」ことが目的です。
歌やゲームを通して英語の音やリズムに触れ、挨拶や簡単な単語表現を楽しく学びます。
文法やテストはなく、聞く・話すが中心です。
小学5〜6年生(教科としての英語:約週2回・年間70回)
- 目的:対象を「読む・書く」領域まで広げ、中学英語への橋渡しをする段階
- 学習内容:
- リスニング・スピーキング:自己紹介、会話のやり取り
- リーディング・ライティング:ローマ字や簡単な文の書き取り
- フォニックスの導入、語彙の拡充、短文構成など学校によっては特色ある授業
- リスニング・スピーキング:自己紹介、会話のやり取り
高学年になると、英語が「成績がつく教科」となります。
内容もステップアップし、読む・書くの要素が加わります。
たとえば、自己紹介や日常の出来事を簡単な英語で書いたり、音声を聞いて選択肢から答えを選ぶリスニング問題も行われます。
評価(通知表)も付けられるため、授業の理解度が今まで以上に求められます。
小学生のうちに英語がなぜ必要なの?

英語が早期に必要とされる背景:グローバル・学習指導要領の変化
2020年から英語学習が変わったという話を聞いたことがある方も多いと思います。
近年、グローバル化が進み、英語力は「将来の選択肢を広げる武器」としてますます重要になっています。
文部科学省もこの流れを受けて、小学生のうちから英語に親しむことを重視するようになりました。
2020年度からは新しい学習指導要領が完全実施され、小学3年生から外国語活動が必修化されました。
これは、「英語が話せるようになる」ことよりも、「英語に慣れて、抵抗感をなくす」ことが目的とされています。
特に日本では、「英語アレルギー」と呼ばれるような苦手意識を持つ子が多い傾向があります。
しかし、小さいうちから英語の音やリズムに触れることで、苦手意識が芽生える前に自然と慣れることができます。
つまり、小学生のうちに英語を始めるのは、将来的な学習のハードルを下げ、
「英語をツールとして活用できる子」に育てる第一歩と考え、このような教育改革が行われているようです。
ちなみに、中学の英語授業も変わっているという話を聞かれたことが多いと思いますので、この後中学英語についても解説しておきますね♪
中学校での英語学習・小学校との違い

中学校での英語学習
中学校での英語の授業スタイル自体は、保護者のみなさんが想像する英語学習とそれほど変化がありません。
テストでの習熟度を測るために、文法を中心とした授業スタイルで、単語テストなども実施されています。
ですが、現在の中学校の英語学習では、「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく育てることが重視されています。
そのため特に、英語で「やり取りする力」や「自分の考えを伝える力」の育成に重点が置かれ、授業は基本的に英語で行われます。
また、2020年の学習指導要領改訂前と比べ、扱う語彙数は約1,200語から1,600〜1,800語に増加。
現在完了などの文法については、高校での学習内容を中学での学習へと前倒しに変更しているため、
保護者の皆さんの中学時代よりもボリュームが多く、速いスピードで学習しているんです。
中学校と小学校の英語学習の違い
ここまで読んでなんとくイメージができた方もいらっしゃるかもしれませんが、
小学校と中学校では、英語学習のレベルに大きなギャップがあります。
■小学校での学習
英語に「慣れること」が目標
■中学校での学習
中学校に入ると一気に「文法」や「読解」「英作文」などの学力評価が加わり、
成績として問われる学習にシフトします。
このような変化をお子さんが前向きにとらえられるようになるために、
まずは小学校の英語学習をきちんと身に着けることが重要なんですね!
中学入学時までにやっておきたい学習目安
改めて、中学入学までに理解しておきたい内容を解説していきます!
小学校の英語授業が導入されたとはいえ、
週1〜2回程度の授業だけでは十分な英語力をつけるのは難しいという声も多くあるんですよね。
(学習塾や通信教育を受講している場合でも、英語学習まで手が回らないという方も多いですよね。)
そのため、中学入学時までにある程度の土台を作っておくと安心ですので、解説していきますね。
一般的に、以下のようなスキルがあると中学英語にスムーズに入れます。
- 英単語(数字・色・動作など)をある程度覚えている
- 簡単な挨拶や自己紹介が言える
- 基本的な会話(例:名前を聞く・答える)が理解できる
- 英語の音声を聞いて、おおよその内容がわかる
また、英語学習の進度を客観的に測る基準として英検5級の取得を目指す家庭も増えています。
英検5級は中学初級レベルの内容なので、小学校で英語を少しずつ進めておけば、無理なく到達できる範囲です。
ただし、すべての子どもが検定を受ける必要はなく、「中学校の授業についていけるだけの準備」として考えると良いでしょう。
重要なのは、英語を「勉強」として構えるよりも、「聞いて、話して、楽しく使うもの」として捉えることです。
小学生の英語学習は何をすればいい?中学入学までの家庭学習方法

低学年は「遊び+音」に親しむことから
小学校低学年では、まず「英語って楽しい!」という気持ちを育てることが何よりも大切です。
英語を学習として構えるのではなく、遊びや生活の中で自然に触れることがポイントです。
たとえば、英語の歌を聴いたり、アニメを英語音声で観たり、英語の絵本を読み聞かせしたりといった活動は、
「音」に慣れる良い機会です。耳が柔らかい時期に多くの英語の音に触れることで、正しい発音やリズムを自然に吸収できます。
また、子ども向けの英語アプリもおすすめです。
遊び感覚で使えるものが多く、気負いなく英語に親しめます。
英語を「勉強」ではなく、「生活の一部」として感じさせることで、長く続ける土台ができます。
中学年・高学年では中学準備を意識してステップアップ
学年が上がるにつれて、英語に求められる内容も少しずつ変わってきます。
中学英語をスムーズにスタートさせるためには、段階的に学習レベルを引き上げていくことが重要です。
■小学校3~4年生
中学年(3~4年生)では語彙を少しずつ増やし、「話す」「聞く」ことに加えて「読む」経験も取り入れていきます。
フォニックス(英語の音と文字の関係)やシャドーイングを取り入れ、お子さん自身が発する練習を取り入れるのがおすすめ。
■小学校5~6年生
高学年(5~6年生)になったら、文法や会話文の練習などにも挑戦していきましょう。
中学年で紹介したシャドーイングやオンライン英会話などを活用し、インプットとアウトプットのどちらも時間をかけられるようになるとよさそうですね。
また、目標をもって取り組みたい方には、英検5級や4級などのチャレンジも有効です。
試験対策を通して「聞く・話す・読む・書く」の4技能を意識的に伸ばすことができ、将来の英語力の基礎がしっかり築けます。
簡単な自己紹介や会話練習などもこの頃から少しずつ取り入れると効果的です。
【学年別のステップアップ例】
- 低学年: 英語の音やリズムに慣れる(歌・絵本・動画)
- 中学年: 語彙や表現を増やし、フォニックスやシャドーイングで音を聞いて発する練習をする
- 高学年: 英検・会話練習・文の構造など中学を見据えた力をつける
こちらもCHECK
-
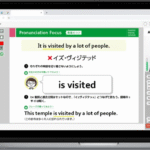
-
Kimini英会話は小学生におすすめ?良い口コミ・悪い評判徹底レビュー
今回はこんなお悩みを解決する記事を書きました💡 我が家は以前kiminiの英会話を受講していた時期があります。ただ、人見知りが激しい子どもなので英語で人と話すことにつかれてしまい、途中で退会してしまい ...
続きを見る
家庭でできる英語学習の具体例
英語は、家庭でも十分に学習できますよ!とくに、毎日少しずつ触れることで、無理なく自然に身についていきます。
- 無料アプリの活用
Duolingoや英語組み立てTOWNなど、無料で始められる英語アプリは低学年~高学年まで幅広く使えます。
毎日5〜10分のスキマ時間で続けやすく、ゲーミフィケーションによって飽きにくいのも魅力です。 - NHKの英語講座(基礎英語など)
小学生向けの番組「基礎英語」などは、英語の音に慣れながら基本の表現を楽しく学べます。 - YouTubeの英語チャンネル
「Super Simple Songs」「Peppa Pig」など、子どもに人気の英語チャンネルは、短くてわかりやすい内容で楽しく英語が聞けます。字幕付きで観ると、「音」と「意味」のつながりも理解しやすくなります。 - 親子での英語遊びや読み聞かせ
英語のかるたやカードゲーム、簡単な英語のやりとり(“What color do you like?”など)を取り入れるのも良い方法です。夜寝る前の読み聞かせを英語の絵本にすることで、日常の中に英語を自然に取り入れる習慣ができます。
家庭学習では、「続けられる工夫」が何より大切です。
無理なく、楽しく、そして少しずつステップアップできる方法を取り入れていきましょう。
こちらもCHECK
-

-
小学生高学年におすすめの英語YouTubeチャンネル7選|フォニックス・物語・文法で楽しく学ぶ
「英語の勉強=むずかしい」と感じていませんか?実は、小学生の英語学習では“楽しみながら慣れる”ことがいちばん大切💡 YouTubeには、フォニックスや童話、アニメを通して自然に英語が身につく動画が ...
続きを見る
ここまで小学校での英語学習について解説してきました。
とはいえ、親が一生懸命になる中で、お子さんが英語の学習に対してちょっと苦手意識を持っているかも…と不安になっている方もいるかもしれませんね。
続いては、小学生が英語を苦手になる理由と対策について解説していきますね。
小学生が英語を苦手になる理由とは?

■英語が苦手になる主な理由
✔「英語=難しい」と感じる最初のきっかけ
✔読み書きが始まると急につまずく
✔音と文字のギャップに戸惑う
✔発表や評価がストレスになることも
小学校の英語学習において、子どもたちが「つまずく」または「苦手になる」主な理由は、
以下のようにいくつかの段階や要因に分かれます。
それぞれのポイントに対して、保護者や指導者が注意しておくことで、英語嫌いを防ぐ手助けになります。
1. 「英語=難しい」と感じるきっかけがある
小学生が英語を「難しい」と感じてしまう背景には、いくつかの原因があります。
たとえば、意味がわからないままフレーズを繰り返したり、日本語との音の違いに戸惑ったりすることで、苦手意識が生まれやすくなります。さらに、自由に発言する活動や、読み書きが増える高学年の授業で「ついていけない」と感じる子も少なくありません。
■主な原因:
- 意味がわからないまま繰り返すだけの授業(特に低学年)
- 英語と日本語の音の違いに戸惑う
- 正解がひとつではない活動(例:自由発言や英会話)に戸惑う
- 読み書きの段階でついていけなくなる(高学年)
こうしたつまずきを防ぐには、英語の意味をイラストやジェスチャーで伝える工夫や、「間違えても大丈夫」と思える安心感のある学習環境が大切です。また、「聞く→話す→読む→書く」という順に少しずつスキルを伸ばしていく段階的な学び方が効果的です。
■対応策:
- 英語のフレーズに絵や身振りなど「意味のヒント」を添える
- 間違えてもOKという雰囲気づくり
- 少しずつ「聞く→話す→読む→書く」に進む段階的な学びが必要
2. 音声中心から読み書きへのギャップ
先ほど解説をしたように、小学校の英語学習では、3・4年生までは「聞く・話す」中心の楽しい活動がメインです。
歌やゲームを通じて自然に英語に親しめるうえ、成績評価もないため、子どもたちはのびのびと学べます。
しかし、5・6年生になると「読む・書く」学習が加わり、英語が教科として評価対象になります。
その結果、アルファベットをうまく書けなかったり、英単語の意味がつかめなかったりすることで、苦手意識を持ち始める子も増えます。自信をなくし、積極的に発言できなくなるケースも少なくありません。
■小3・4年までは:
- 歌・ダンス・ゲーム中心の「聞く・話す」がメイン
- 成績評価がなく、楽しく学びやすい
■小5・6年になると:
- 「読む」「書く」学習が加わる
- 成績(通知表)に反映されることでプレッシャーが強まる
■つまずく例:
- アルファベットを正しく書けない
- 英語の単語が読めない・意味がつかめない
- 自信を失って発言を控えるようになる
上記のように、つまづくお子さんが多いと思いますので、
アルファベットや単語を聞いて発音する練習をすることで、苦手意識を減らすことがとっても重要!
そのうえで、アルファベットの書き方や、単語の読み方やつづりを少しずつ学習の中に取り入れていきます。
■対応策:
- ローマ字との違いを明確にする(例:英語はつづりと発音が一致しないこともある)
- フォニックスやシャドーイングの導入で「音とつづり」を結びつける練習が有効
- 書く学習の前に、十分なリスニング経験を積む
3. 成績がつくことへのプレッシャー
高学年になると、英語が教科として扱われ、通知表に評価がつきます。
特に次のようなことが苦手意識を生みます。
- 「できない=悪い評価」と受け止めてしまう
- 発音や表現が「正しくない」と指摘される体験
- グループワークや発表で恥ずかしさを感じる
対応策:
- 家庭では結果よりも「取り組む姿勢」や「頑張り」を褒める
- ミスを恐れない環境をつくる
- 小さな「できた!」を積み重ねる(チャートやスタンプなども有効)
英語が苦手になる背景には、「急なステップアップ」や「周囲との比較」が大きく関係します。
特に、音→文字→意味の段階的理解が欠けると、学習が「作業」になりやすく、楽しさが失われます。
だからこそ、
- 子どものレベルに合った方法
- 興味を引き出す教材
- 家庭での声かけとサポート
これらを意識することが、英語への苦手意識を減らし、自信につながる第一歩となりますよ!
よくあるQ&A
Q. 早く始めすぎると逆効果にならない?
A. 無理に「勉強」として取り組ませると、確かに逆効果になることがあります。ですが、「遊び」や「音楽」「絵本」などを通じて自然に英語に触れさせる分には、早すぎるということはありません。とくに小学校低学年までは、英語の音に親しむ「耳の黄金期」。日本語と同じように、言葉を感覚で吸収できる時期なので、楽しく触れる体験はむしろプラスになります。
注意点は、「読み書き」を急がないこと。アルファベットや単語を無理に覚えさせようとすると、英語への苦手意識につながりかねません。**「楽しい」「わかる」「まねしたくなる」**が続くように、年齢に合った方法で進めていくのがポイントです。
Q. 親が英語が苦手でもサポートできる?
A. はい、大丈夫です!英語が話せなくても、子どもと一緒に学ぶ気持ちがあれば十分サポートできます。大切なのは、「一緒に楽しむ姿勢」です。
たとえば、
- 英語の歌を一緒に聞いて楽しむ
- 絵本を一緒に見る(読み上げは音声アプリやCDにおまかせでもOK)
- 動画やアプリを一緒に体験して、「これ面白いね」と声をかける
このような関わりだけでも、子どもにとっては安心感やモチベーションにつながります。
さらに、YouTubeやNHKの英語講座などには、保護者向けの解説やサポートもあるので、必要なときに情報を調べながら進められます。最近は、保護者自身も「一緒に英語を学び直す」ことを楽しんでいるご家庭も増えています。
こちらもCHECK
-
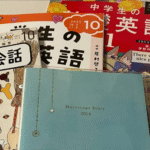
-
NHK「小学生の基礎英語」を3年継続!苦手だった英語が得意に変わった理由
今回はこんなお悩みを解決する記事を書きました。 これまでNHKの語学講座「小学生の基礎英語」を3年間続けてきていますが続けたことでの変化や子どもの感想、なぜお勧めできるのかをご紹介していきますね♪ こ ...
続きを見る
Q. 英語以外の教科とのバランスは?
A. 英語学習はあくまで日常の中で自然に取り入れるスタイルがおすすめです。国語や算数と違い、「1日30分しっかり机に向かう」というよりも、「毎日少しずつ続ける」ことが大切です。
たとえば、
- 朝の支度中に英語の音楽を流す
- 就寝前に英語の絵本を1冊読む
- アニメを見る時間を英語版に切り替えてみる
このように、他教科の学習を圧迫しない工夫をすれば、英語と他の教科を両立することは十分可能です。特に小学生のうちは、「英語が生活の中にある」ことを意識させるだけでも十分な効果があります。
また、英語を早くから学ぶことで、国語力(読解力)や論理的思考力にも良い影響を与えるという研究もあります。無理なく楽しく、生活に溶け込むように進めていきましょう。
まとめ
小学校の英語学習は、中学校以降の本格的な英語教育への土台を築く大切な時期です。
家庭でも、英語アプリや動画、絵本の読み聞かせ、オンライン英会話などを活用し、日常的に英語に触れる機会を作ることが効果的です。子どもの年齢や興味に合わせた学習法を取り入れながら、楽しく続けることが将来の英語力向上につながります。親子で協力しながら、無理なく自然に英語を生活の一部にしていくことが、成功の鍵となりますよ。
今回の記事が参考になれば幸いです。